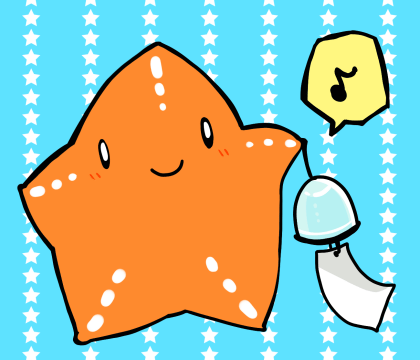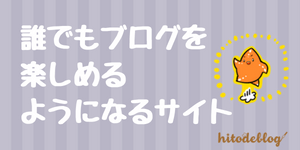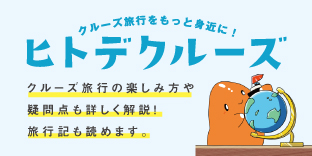・意識した点
・「バカとテスト召喚獣」を読んで、会話ベースで進むとテンポが良い事に気付いたのでその実験
・読みやすさ
・前回に引き続き「ラノベらしさ」(=萌え?)
・5分くらいで読めます
今回は行間あえて空けないでいるけど、空けた方が見やすかったら教えてください
積極的なメリーさん
「私、メリーさん。あなたの事が好きです」
「……今何て?」
突然かかってきた電話。突然の愛の告白。突然すぎてまるで意味がわからない。何だこれ。
「あなたの事が好き。付き合ってほしい」
「い、いや、誰?」
「私? 私はメリーさん」
「と、とりあえず考えさせて……」
逃げるように電話を切る。深呼吸。大きく吸って、ゆっくり吐く。よし、俺は冷静だ。頭がおかしくなったわけではない。それは間違いない。どうしてこうなったのか、よく考えよう。
一人暮らしの部屋のベッドに腰を掛けて今日一日を反芻する。起きて、大学に行って、買い物して、帰ってきて、飯食って、風呂入って、そしたら電話かかってきて、告白をされた。
……なるほど。全然わからん。
そもそも彼女は誰なのか。若い女の声で「メリー」と名乗ったが、俺の知り合いにそんな奴はいないはず。
そうだ、着信履歴。携帯の着信履歴には番号が残っているはずだ。
はずなのだが……。
「ない……」
つい数分前、俺は確かに電話をしていた。にも関わらず着信の記録は残っていない。これは一体……。
同時に手元の携帯が震えた。驚きのあまり落としかけるが何とかキャッチ。ディスプレイには真っ黒な画面に白い文字で「メリー」とだけ書かれている。番号はおろか他には何も映っていない。故障だろうか。
中々不気味だし、出るべきか悩んだが、正直放っておく方が怖い気がしたのでもう一度深呼吸をしてから通話ボタンを押した。
「……もしもし?」
「私、メリーさん。ねえ、考えてくれた?」
「いや、それはまだちょっと……。っていうか『メリーさん』って、あの怪談のメリーさんから取ったの?」
「取ったっていうか、私がその『メリーさん』だよ?」
あ、これやばい奴だ。
「この前あなたの事、偶然町で見かけたの。一目ぼれしちゃったの。だから付き合ってほしい。ね、いいでしょう?」
「いいわけないだろう」
「何で?」
「だって俺、君のことよく知らないし。いきなりそんな風に言われても、その、困るよ」
いや、そんな問題ではないような気もするが。とりあえず出てきた言葉がそれだった。
「……わかった」
わかってくれたらしい。
「それじゃあ、これから知ってもらうね」
「え?」
「じゃあ、また明日ね?」
「え!?」
この日から、メリーさんのアプローチが始まった。
翌日、まったく同じ時間に携帯が震える。まさかとは思ったがやはり着信画面には「メリー」の三文字。しばらく放置してみるも、着信が止む様子はない。覚悟を決めて、通話ボタンを押した。
「はい、もしもし」
「私、メリーさん。今日のパンツはピンクなの」
「それ言わなくていいよね!?」
「じゃあ、何を言えばいいの……?」
「普通のメリーさんは位置とかいうと思いますけど」
「そんな……恥ずかしいよ……」
「パンツの位置じゃねーよ!」
なんだこれ疲れる。一度冷静になろう。深呼吸だ。深呼吸は万能だ。とにかく吸って、とにかく吐く。うん。せめて、まともな会話をしよう。
「どうして、位置を教えるの?」
「そうやって段々近づいて来るんだよ。『今あなたの住んでる町にいるの』『今あなたの家の前にいるの』『今あなたの部屋の前にいるの』って具合に」
「それで?」
「最終的には『今あなたの後ろにいるの』って終わるのが普通だけど……」
自分で言っていて、嫌な予感がした。そしてそれは即座に当たった。
「それ、いただき」
「いただくな!」
「私、メリーさん。最終的にはあなたの心の中に入り込みたいの」
「目的を定めるな! っていうか後ろどころじゃねーよ! 重いよ!」
「うふふ、私頑張る。じゃあ、また明日ね?」
「頑張るって何を!?」
俺の問いかけに答える前に電話は切れた。相変わらず履歴は残っていない。誰かに相談しようかと考えるが、こんな話を誰が信じるというのか。大きくため息をついてから、いつもより厳重に戸締りをチェックしてから眠りについた。
あれから二週間たったこの日も、案の定電話はかかってきた。前もって電源を切っておいたのだが、そんなことはおかまいなしに携帯は震え続ける。あれから毎日、必ず同じ時間に電話がかかってきている。
そのまま放っておいても、留守番電話に繋がらないことは知っていた。かれこれ2、3分は鳴りっぱなしだが、この前は3時間なり続けた。それどころかどんどん振動が強くなっていくのだ。
冷蔵庫からお茶を取り出してコップ一杯分を飲み干してカラカラになった喉を潤す。覚悟を決めた。もうこいつの戯言に惑わされてたまるか。通話ボタンを押す。
「……はい」
「私、メリーさん。今あなたの家の前にいるの」
「展開はえーよ!!」
思わず携帯をベッドに投げつける。ワンバウンドしたそれを見下ろしながら深呼吸。落ち着け、ペースに飲まれちゃダメだ。なんとか落ち着いてから携帯を拾い上げ、ベッドに腰掛けて話を戻す。
「ほ、本当なのか……?」
「嘘」
「ぶん殴りてぇ……」
「だって、本当は、部屋の前にいるの」
「……は?」
ドッと心臓が跳ね上がる。冷や汗が即座に全身を覆った。室内なのに寒気が止まらない。息がうまく吸えない。情けなく息を漏らしながら玄関に目をやる。
何か……「いる」……。
「入るね?」
「え?」
鍵がかかっているはずの扉が自然に開いた。その先に立っている女性。まっさきに足元を見るが、足はある。真っ暗なワンピースに身を包み、それとは逆に透き通るような白い肌の少し小柄な少女だった。俯いているせいでぱっつんの前髪が目元に影を落としている。表情は一切読み取れない。でも、片手に電話を持っていた。
「私、メリーさん」
電話と目の前の声がダブって聞こえる。俺はというと、この非現実的な状況に立ち上がることもできないまま、ただ口を阿呆みたいにぽかんとあけているのだった。
「今、あなたの目の前にいるの」
少女が顔を上げて、笑顔を見せた。びっくりするほど優しい笑顔で、俺のイメージした幽霊の不気味な笑顔とはまるで違っていた。そのせいで、不覚にも心臓が跳ねた。
「でもね、今日でお別れ」
「……え?」
「もうね、行かなくちゃいけないの。だから最後に、会いに来ちゃった」
未だに動けないでいると、足音もなく少女はこちらに歩いてきた。
「私、生きてる時は誰かを好きになったことなんてなかったのに。こんなに、ドキドキするんだね。最後に知れてよかった。ありがとう」
電話が切れた。いつもならそれでメリーさんと俺との会話は終わりだが、今日は違う。なぜなら彼女は、すぐ目の前にいるのだ。
そっと俺の横に腰を降ろす少女。何か言葉をかけるべきなのに、何も思い浮かばない。何も話しかけることができない。
俺の肩にもたれるように体重をかけてくる。女の子特有の柔らかい体の感触が伝わってきた。ふわり、と石鹸のような香りが鼻腔をくすぐる。幽霊でも、いい匂いするんだ……。
「私、メリーさん」
電話を通さない、初めての生の声。透き通るような白い肌に少し赤みが増している。
「今、あなたの隣にいるの」
メリーさんは、照れたように笑った。
向日葵のような、暖かい笑顔だった。でも、涙が出るのは何故だろう。
何か言葉を、せめて、最後に彼女に言葉を贈ろう。
そう思って口を開いた途端、何の前触れもなく少女の姿は消えた。肩への心地よい重さも同時に失われた。
唖然とする。
「……嘘だろ」
だって、俺はまだ何も言ってない。何も、言ってないじゃないか。
「ふざけんな!」
ベッドから跳ねるように飛び起き、部屋中を見渡す。もちろん俺以外に誰もいない。扉にだって内側から鍵がかかっている。なんだ? 俺は頭がおかしくなったのか? それとも夢でも見てたのか?
ふと地面に落ちていた携帯電話が目に入る。チカチカと点滅していた。拾い上げるとディスプレイに文字が表示されている。
『留守番電話 1件』
何も考えずに即座にメッセージを再生すると、聞きなれた声が聞こえた。
『私、メリーさん。いつまでもあなたの心の中にいるの』
ほんの5秒もないようなメッセージは、なぜかもう一度聞こうとしても「データが破損しています」と表示されるだけで聞くことはできなかった。でも、たった一回でも確かに聞いた。それで、十分だった。
「あーあ。負けたなー」
誰に言うでもなく呟いた。彼女の思惑通り、俺はメリーさんの事を忘れることなどできそうにない。まさに、心の中に入り込まれてしまったのだ。
ベッドに腰掛け、彼女との今までの会話を思い出しながら倒れこむ。
「いたっ!」
頭に、何かが当たった。
バッと振り返ると、隅っこに寄せてあった掛布団が不自然に膨らんでいる。これは……。
一気に掛布団を引きはがすと、丸まった黒いワンピースの少女、メリーがいた。いたずらを見つかってしまった子供のような顔をしている。
「これは……どういうことだ……?」
「えっと、これくらい演出したら心に残るかなーって」
「……」
「どうだった? ねえ、私の事好きになった? 心に残った?」
「とりあえず……」
「とりあえず?」
「出てけェ――――!!」
メリーさんに振り回される日はこれからも続く。